大脳基底核の役割と病変
大脳基底核は、尾状核、被殻、淡蒼球(外節GPl・内節GPm)、視床下核(STN)、黒質(緻密部SNc ・網様部SNr)から構成される灰白質の神経核群です。大脳皮質からの入力を受けて運動出力を調整し、随意運動の開始・強度・滑らかさをコントロールします。ここでは、大脳基底核の主な働きと、その障害によって生じる代表的な疾患について解説します。
大脳基底核の働き
大脳基底核は、大脳皮質からの興奮性入力を受け、視床を介して大脳皮質に出力をフィードバックすることで運動出力を調整しています。調整には複数の神経経路があり、以下の4つに分けて考えます。 なお、近年の神経生理学的研究により、大脳皮質から視床下核を介して直接淡蒼球内節へ至る「ハイパーダイレクト経路」の存在も確認されています。この経路は運動の即時抑制や反応停止に関与するとされますが、その機能的意義は現在も研究が進められています。
- 主経路(直接経路)
- 副経路(間接経路)
- 黒質緻密部からの主経路への作用(D1経路)
- 黒質緻密部からの副経路への作用(D2経路)
1.主経路
大脳皮質は線条体(興奮性=グルタミン酸)を興奮させます。線条体(抑制性=GABA)の興奮により、淡蒼球内節(GPm)および黒質網様部(SNr)を抑制します。GPm/SNrはいずれもGABA作動性の出力核として視床を抑制していますが、これらが抑制されることで視床への抑制が解除(二重抑制=脱抑制)され、視床が活動しやすくなります。結果として、大脳皮質への興奮性フィードバックが増強し、大脳皮質からの出力が増大します。
機能要約:この経路は主に視床—大脳皮質ループを介して運動出力を促進し、脳幹への運動関連出力も増強させます。
2.副経路
大脳皮質は線条体を興奮させ、線条体は淡蒼球外節(GPl)を抑制します。抑制されたGPlでは視床下核(STN)への抑制性入力が減少し、STNが活動しやすくなります。活性化したSTNは淡蒼球内節(GPm)を興奮させ、GPmから視床への抑制性入力を増大させます。その結果、視床の活動が抑制され、大脳皮質への興奮性フィードバックが減弱し、大脳皮質からの出力は低下します。
機能要約:この経路は“ブレーキ回路”として働き、不要な運動や過剰な活動を抑制します。
3.黒質緻密部の主経路への作用(D1)
黒質線条路から放出されるドパミンは、D1受容体を介して主経路を促進する方向に働きます。具体的には、SNc からのドパミンが線条体D1ニューロンを興奮させ、線条体がGPmをより強く抑制することで、視床の脱抑制が起こります。これにより視床が活動しやすくなり、大脳皮質への興奮性フィードバックが増強して、大脳皮質からの出力が増大します。
4.黒質緻密部の副経路への作用(D2)
SNc から放出されたドパミンは、線条体D2ニューロンの活動を抑制します。これにより線条体からGPlへの抑制が弱まり、GPlが脱抑制されます。脱抑制されたGPlはSTNを抑制し、STNからGPmへの興奮性入力が減少します。結果としてGPmの活動が低下し、視床への抑制が弱まります。活動しやすくなった視床は大脳皮質への興奮性フィードバックを増強し、大脳皮質からの出力を増大させます。
機能要約:ドパミンはD1系とD2系の両経路を介して運動出力を促進する方向に働いており、そのバランス破綻は運動障害に直結します。
大脳基底核の病変
大脳基底核の障害によって運動麻痺は生じません。すなわち、麻痺(錐体路障害による筋力低下)ではなく、動作の“出し入れ”(開始・停止)や“リズム”(速度・滑らかさ)の異常として現れるのが特徴です。これは、大脳基底核が「運動の発生」そのものではなく、「運動の調整」に関与しているためです。そのため、障害時には筋緊張の異常や不随意運動が主症状として現れます。
臨床の要点
- 錐体路サイン(徒手筋力低下、腱反射の著明亢進、Babinskiなど)よりも、寡動・動作開始困難・運動の減衰(sequence effect)・姿勢反射障害などの評価が診断的に有用。
- 歩行観察では歩隔、腕振り、立ち直り、すくみ足、方向転換時の一過性停止を重点確認。
- 在宅・病棟では、立ち上がりの初動遅延や微小課題での運動量低下をルーチン観察項目に。
代表的疾患
パーキンソン病(PD)
パーキンソン病は黒質緻密部(SNc )の変性により、線条体へのドパミン入力が低下する神経変性疾患です。これは前述したD1(直接)・D2(間接)経路に対するドパミン作用の減弱に相当し、両経路のバランスが崩れて大脳皮質への出力が低下します。その結果、寡動・無動・筋固縮などのパーキンソン症状が出現します。
臨床像の具体例:動作開始困難、歩行時のすくみ足、小刻み歩行、書字の小字症、姿勢反射障害、安静時振戦など。疾患は徐々に進行します。
治療概略:L-ドパ、ドパミンアゴニスト、MAO-B阻害薬、COMT阻害薬、アマンタジンなどで不足ドパミン作用を補い、回路機能の相対的正常化を目指します(症状・年齢・合併症で選択)。外科的にはSTN/GPmへのDBSが対象となる症例があります。
片側バリスム(Hemiballism)
片側バリスムは、視床下核(STN)の病変によって生じる過運動性疾患です。STNはGPmを興奮させる役割を持つため、その機能が失われるとGPmの活動が低下し、視床が脱抑制されます。その結果、大脳皮質の運動出力が過剰となり、対側四肢に粗大な不随意運動(バリスム)が出現します。
病因:脳梗塞や脳出血などの血管障害が主因。発症直後に症状が最も強く、時間経過とともに自然軽快する傾向がありますが、改善経過には個人差があり、病変範囲や残存機能により舞踏様運動を残す場合もあります。
まとめ
大脳基底核は、運動そのものを生み出すのではなく、運動の「選択」「開始」「強度」「停止」といった出力調整を担う中枢です。主経路・副経路・黒質線条路の相互作用により、視床—大脳皮質間ループの興奮と抑制のバランスを精緻に制御しています。このネットワークの均衡が崩れると、パーキンソン病のような低運動状態や、片側バリスムのような過運動状態として臨床的に現れます。
臨床的含意:大脳基底核は「動く・止まる・調整する」を司る運動制御のゲートとして働きます。この理解は、単なる解剖学にとどまらず、ベッドサイドで「なぜ動きがぎこちないのか」「なぜ止まれないのか」を考える上で不可欠です。
次回予告:ループ系と高次機能
次回は、この制御回路が脳全体の情報処理とどのように結びついているかを整理します。大脳基底核のループ系には、運動制御だけでなく、認知・情動・意思決定といった高次機能に関わる複数のサブネットワークが存在します。具体的には、以下の4系統です。
- 運動・感覚野ループ系
- 連合野ループ系
- 動眼系ループ系
- 辺縁系ループ系
それぞれが異なる皮質領域と連携し、「動く」「感じる」「考える」「感じ取る」といった多面的な行動制御を支えています。次回は、これら4系統の構造と機能を整理し、臨床動作分析やリハビリテーションへの応用の基盤として解説していきます。
参考文献
脳MRI 1.正常解剖 第2版 高橋昭喜 編著※このリンクにはアフィリエイト広告が含まれます。 記事内容は筆者の専門的知見に基づき、公平な情報提供を行っています。
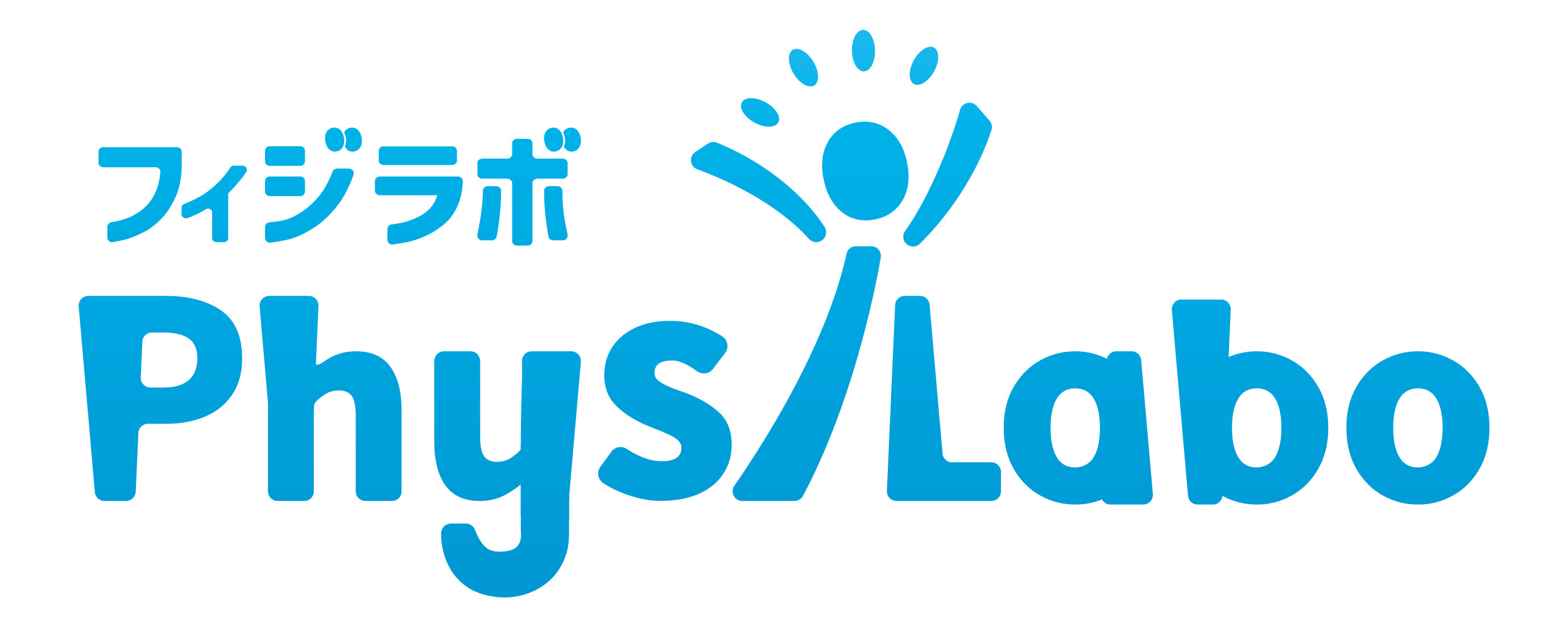
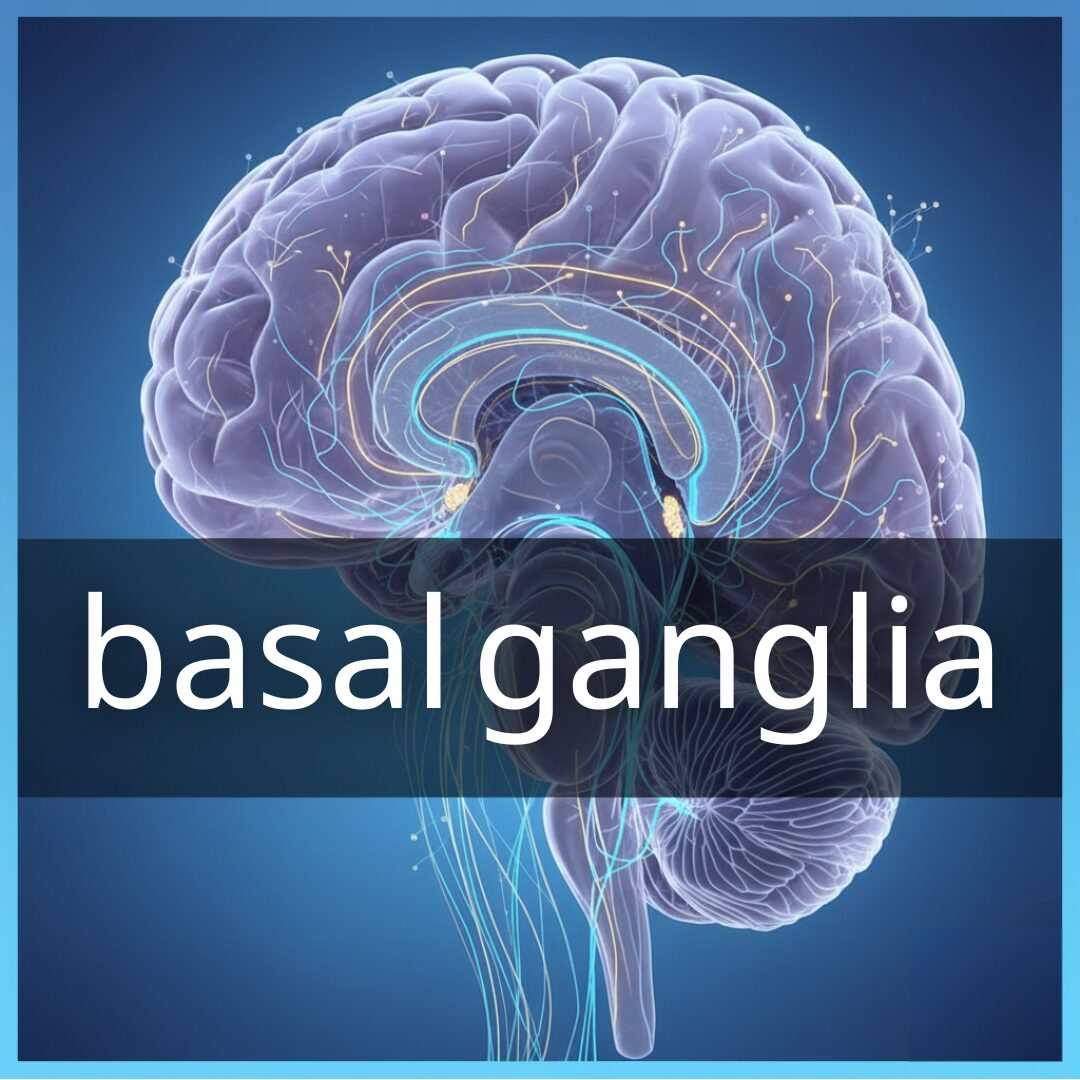
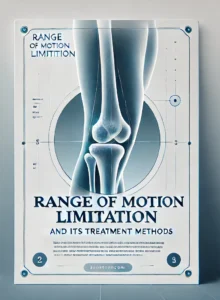
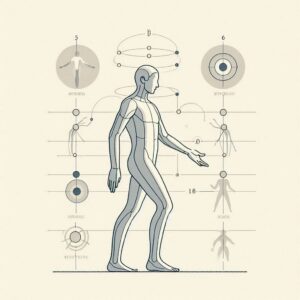
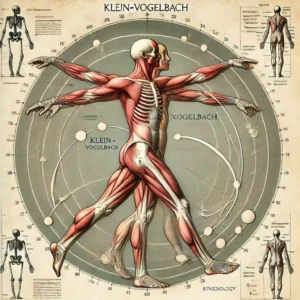
コメント